2023 年 5 月に「Generative AIセンター」を設置し、社内外への生成 AI の利活用に取り組んでいる日立製作所。その中で、システム開発領域における利活用の一環として行われているのが、GitHub Copilot の活用です。同社では、ベンダー ロックインを回避できグローバル スタンダードになり得る開発ツールの 1 つとして、2021 年から GitHub を活用していますが、その延長として GitHub Copilot による開発生産性向上に取り組んでいます。
まず 2023 年 10 月に GitHub Copilot 活用の効果に関する社内評価をスタート。また GitHub Copilot 単体だけではなく、日立製作所が既に持っている開発フレームワークと連携させた活用も行われています。さらに、これらの取り組みで得られたナレッジを蓄積および共有するため、2024 年 4 月に「生成AI実務者コミュニティ」を発足。生成 AI 活用の「拡大」だけではなく「定着度」を強く意識した活動が展開されています。
社内評価では「タスクを迅速に完了できる」が 83% に上るなど、高い評価を受けているのに加えて、実際に生産性が 30% 向上したケースも登場しています。また開発フレームワークとの連携では、業務ロジックのコード生成率が ルールベースのみの78% から GitHub Copilotの併用で99% へと向上した例もあります。コミュニティ活動では、ナレッジの審査/承認/発信を行うモデレーターを置くことでナレッジの品質担保と体系化を実現。生成 AI 活用の定着度向上に貢献しています。













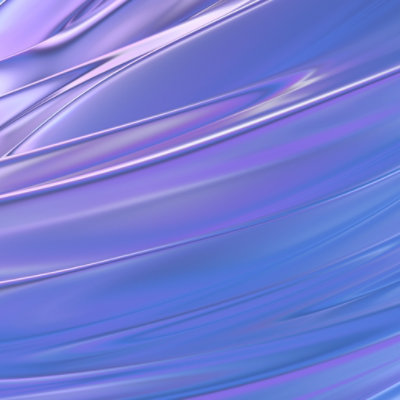




Microsoft をフォロー